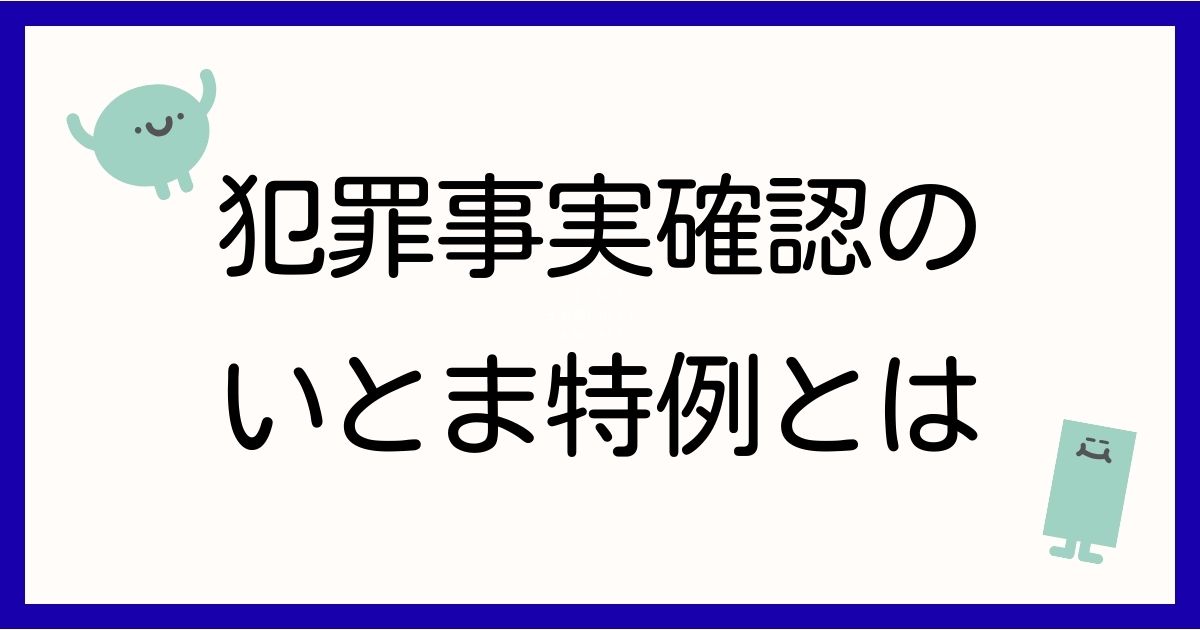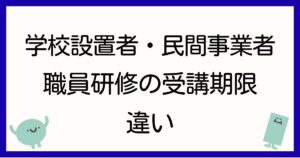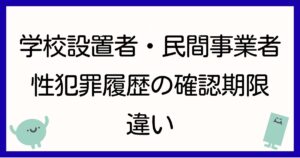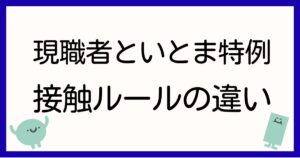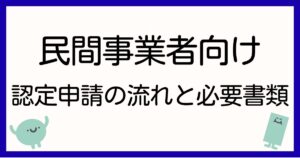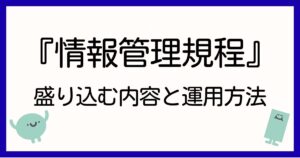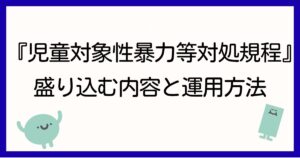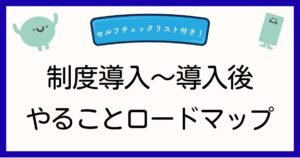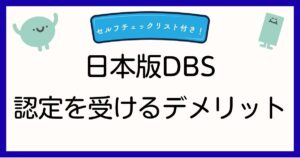いとま特例とは?
2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」では、教育・保育事業者に対して従事者の犯罪事実確認が義務付けられます。
通常、この確認は業務開始までに行うことが原則とされていますが、特定の状況では例外的な取り扱いが認められています。これが「いとま特例」です。
やむを得ない事情により業務開始までに犯罪事実確認を行う時間がない場合に、業務に従事させた日から6ヶ月以内で政令で定める期間内に確認を行うことができる特例制
なぜいとま特例が設けられたのか?
教育・保育の現場では、以下のような緊急事態が発生することがあります。
- 急な欠員の発生
病気や怪我、急な退職により、教員・保育士が不足する事態 - 新設や合併
新しい施設の開設や組織変更に伴う大量採用の必要性 - 労働者派遣
派遣会社からの紹介で、契約締結が遅れるケース
このような状況で犯罪事実確認を待っていると、子どもたちの教育・保育に支障をきたす可能性があります。
いとま特例は、子どもの最善の利益を守りながら、安全確保措置も両立させるための制度なのです。
いとま特例の重要な特徴
いとま特例には、事業者が理解しておくべき重要な特徴があります。
特例適用中の重要な義務
いとま特例を適用している間、事業者は当該従事者を特定性犯罪事実該当者とみなして、性暴力防止のために必要な措置を講じなければなりません。
つまり、いとま特例は単なる「確認の先延ばし」ではなく、より厳格な安全管理体制のもとで業務に従事させることが前提となっています。
次の章では、具体的にどのような「やむを得ない事情」でいとま特例が適用されるのかを詳しく解説します。
いとま特例が適用される「やむを得ない事情」とは
いとま特例を適用するためには、法律で定められた「やむを得ない事情」に該当する必要があります。
ここでは、現在想定されている具体的な事例を分かりやすく解説します。
急な欠員が生じた場合
最も典型的なケースが、教員や保育士等に急な欠員が生じた場合です。
- 担任教師が急病で長期入院することになった
- 保育士が家族の急病で急遽退職することになった
- 事故や怪我により職員が急に業務継続できなくなった
- インフルエンザなどの感染症で複数の職員が同時に休職した
このような場合、子どもたちの安全確保や教育・保育の継続のために、緊急で代替職員を配置する必要があります。
労働者派遣・請負契約に関わる場合
派遣会社や請負業者から人材を受け入れる際の特殊事情も対象となります。
- 派遣会社との契約締結が事業者の責任ではない事情により遅れた
- 請負契約で清掃業務を委託していたが、急に業者変更が必要になった
- 給食調理の委託先が急に変更になり、新しい調理スタッフが配置された
これらのケースでは、事業者が直接コントロールできない外部要因により、確認手続きが間に合わない状況が生じます。
組織変更に伴う大量採用の場合
新設合併や吸収合併など、組織の大幅な変更に伴って短期間で多くの職員を採用する必要がある場合も対象です。
- 複数の保育所が合併して新しい認定こども園を設立する
- 学校法人の統合により、職員の再配置が必要になった
- 新校舎の開設に伴い、大量の教員採用が必要になった
このような大規模な変更では、全職員の犯罪事実確認を一度に処理することが物理的に困難な場合があります。
採用決定から業務開始までの期間が短い場合
新規採用や異動の決定から実際の業務開始までの期間が短く、犯罪事実確認の手続きが間に合わないケースも含まれます。
- 年度途中の急な転任や配置換えが決定した
- 産休・育休代替職員の急な手配が必要になった
- 内定通知から入職までの期間が2週間以内と非常に短い
ただし、通常の新卒採用や定期的な人事異動など、事前に予測可能な場合はやむを得ない事情に該当しない可能性があります.
やむを得ない事情の判断基準
やむを得ない事情に該当するかどうかは、以下の要素を総合的に判断することになります。
- 緊急性:事態の発生が急で、事前の予測や準備が困難だったか?
- 事業者の責任範囲:事業者がコントロールできない外部要因によるものか?
- 子どもへの影響:確認を待つことで子どもの教育・保育に重大な支障が生じるか?
- 代替手段の有無:他に現実的な解決方法が存在しないか?
次の章では、いとま特例を適用する際に事業者が必ず実施しなければならない義務と対応について詳しく解説します。
いとま特例適用中の事業者の義務と対応
いとま特例を適用する場合、事業者には通常の従事者よりも厳格な安全管理措置が求められます。
「確認が後回しになる分、より注意深く管理する」という考え方が基本となります。
特定性犯罪事実該当者とみなした管理
いとま特例適用中の従事者は、特定性犯罪事実該当者とみなして性暴力防止のために必要な措置を講じなければなりません。
これは非常に重要な義務です。
つまり、犯罪歴があるかどうか分からない状態であっても、「あるものとして扱う」ということになります。
具体的な安全管理措置
いとま特例適用中に実施すべき具体的な措置をご紹介します。
1.単独での子どもとの接触を避ける
- 複数職員での対応
必ず他の職員と一緒に子どもに接するよう配慮する - 密室状況の回避
個別指導や相談の際は、扉を開けておく、ガラス張りの部屋を使うなど - 保護者への事前説明
可能な範囲で保護者に状況を説明し、理解を得る
2.業務範囲を制限する
- 身体接触を伴う業務の制限
着替えの手伝い、身体ケア、医療的ケアなどは他の職員が担当 - 課外活動の制限
宿泊を伴う行事や課外活動への参加を制限または複数体制にする - 責任範囲の明確化
担当できる業務とできない業務を明文化し、他の職員と共有する
3.監視・記録体制の強化
- 定期的な行動確認
管理職による定期的な見回りや業務状況の確認 - 業務記録の詳細化
日々の業務内容や子どもとのかかわりを詳細に記録 - 他職員による情報共有
チーム内で当該職員の業務状況を共有し、異常がないか確認
4.研修と指導の実施
いとま特例適用中の従事者に対しては、特別な研修や指導も必要です。
- 性暴力防止に関する基礎知識
子どもの権利、適切な接し方、不適切な行為の理解 - 適切な距離感の保持
子どもとの身体的・心理的な距離の取り方 - 組織のルールと期待
施設独自のルールや行動規範の徹底 - 報告・相談体制
困った時の相談先や報告方法の確認
保護者や関係者への対応
いとま特例を適用する際の、外部への説明や対応も重要な要素です。
- 安全管理の強化
「安全管理をより強化している」という前向きな説明 - 制度の正当性
法律に基づく適切な手続きであることの説明 - 期間の明示
一時的な措置であり、確認完了後は通常体制に戻ることの説明
リスク管理体制の構築
いとま特例適用中は、通常以上にリスク管理体制を整備する必要があります。
- 緊急時対応計画
問題が発生した場合の迅速な対応手順を策定する - 相談窓口の活用
子どもや保護者からの相談を受け付ける体制を強化する - 外部専門家との連携
必要に応じて児童相談所や警察との連携体制を確認しておく
次の章では、いとま特例の具体的な手続きと期間について詳しく解説します。
いとま特例の具体的な手続きと期間
いとま特例を適用する際の具体的な手続きの流れと、守るべき期間について詳しく解説します。
適切な手続きを踏むことで、法令違反を避けながら、緊急時にも適切に対応できます。
いとま特例の適用期間
業務に従事させた日から3ヶ月以内に犯罪事実確認を完了させる必要があります。
現時点では政令で具体的な期間は決定されていませんが、可能な限り早期に確認を完了させることが求められています。
- 業務開始日の記録
いとま特例を適用して業務を開始した正確な日付を記録 - 確認完了予定日の設定
3ヶ月以内の具体的な確認完了目標日を設定 - 進捗管理
確認手続きの進捗状況を定期的にチェック
手続きの流れ
いとま特例を適用する場合の標準的な手続きの流れをご紹介します。
- 緊急事態の内容と原因を詳細に記録
- 他に現実的な代替手段がないかを検討
- 管理職による適用可否の判断
- 適用決定の理由を文書化
いとま特例の適用を決定したら、直ちに安全管理措置を実施します。
- 特定性犯罪事実該当者とみなした管理体制の構築
- 業務範囲の制限と他職員への周知
- 監視・記録体制の開始
- 当該従事者への研修・指導の実施
安全管理措置と並行して、犯罪事実確認の手続きを速やかに開始します。
- 従事者への制度説明と同意取得
- 必要書類の準備と申請手続き
- 内閣総理大臣への照会申請
- 結果通知の待機と進捗確認
- 安全管理措置の解除
- 通常の業務体制への復帰
- 職員・保護者への状況報告
- 記録の整理と保管
- 性暴力防止のために必要な措置の継続・強化
- 配置転換や業務内容の見直し
- 関係部署への報告
- 被害防止のための追加措置の検討
記録・報告義務
いとま特例を適用した場合、適切な記録と報告が法的に求められます。
- 適用理由
やむを得ない事情の具体的内容と発生日時 - 対象者情報
いとま特例を適用した従事者の氏名、業務内容、配置場所 - 安全管理措置
実施した具体的な措置内容とその期間 - 確認手続き
犯罪事実確認の申請日、結果通知日、判定結果 - 事後対応
結果に基づいて実施した措置や体制変更
📝報告義務
いとま特例の適用については、適切な報告が求められる場合があります。
- 所管庁への報告
学校や認可保育所などは、所管する教育委員会や自治体への報告が必要な場合があります - 定期報告での記載
法律に基づく定期的な実施状況報告において、いとま特例の適用実績を記載 - 監査・検査への対応
行政監査や第三者評価の際に、適用記録の提示が求められる可能性
注意すべきタイミング
いとま特例の手続きで特に注意すべきタイミングがあります。
確認完了期限の管理
期限管理の重要性
3ヶ月以内の期限を過ぎると法令違反となってしまいます。余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です
手続き遅延のリスク
- 申請書類の不備
必要書類に不備があると手続きが遅延する可能性 - 繁忙期の影響
新年度など申請が集中する時期は処理に時間がかかる可能性 - 従事者の協力
従事者本人の協力が得られない場合の対応策を事前に検討
次の章では、いとま特例適用時のリスク管理について、より実践的なポイントを解説します。
緊急時の対応計画
事業者は、いとま特例を適用させるときに備えて必要な計画を立て、継続的に実行できるように準備を進めておきましょう。
具体的な計画内容や実行項目は以下の通りです。
準備すべき対応計画
- 連絡体制
管理職、保護者、関係機関への緊急連絡の手順を作成する - 事実確認
問題発生時の迅速かつ適切な事実確認の方法 - 被害防止
追加被害を防ぐための即座の措置 - 外部対応
メディアや行政機関への対応方針
関係機関との連携
- 児童相談所との連携
子どもの保護や支援に関する連携体制の構築 - 警察との協力
犯罪性が疑われる場合の迅速な通報体制 - 行政機関への報告
所管庁への速やかな報告と相談体制
継続的な改善のための取り組み
いとま特例の適用経験を活かして、組織全体の安全管理体制を向上させることも大切です。
振り返りと評価
- 適用結果の検証
いとま特例の適用が適切だったかを事後に検証する機会を設ける - 課題の抽出
運用上の問題点や改善すべき点を整理する - ベストプラクティスの共有
うまくいった取り組みを組織内で共有する
予防的措置を強化する
- 採用プロセスの見直し
緊急採用が必要にならないよう採用計画を改善する - 代替要員の確保
急な欠員に対応できる代替要員の事前に確保しておく - 研修体制の充実
全職員の安全意識を向上するための研修内容を強化する
最後の章では、これまでの内容をまとめて、事業者が今すべきことを整理します。
まとめ【事業者が今すべきこと】
いとま特例は「緊急時の安全確保制度」
単なる確認の先延ばしではなく、より厳格な安全管理のもとで業務を継続させる制度です。
- 限定適用:「やむを得ない事情」がある場合のみ
- 厳格管理:特定性犯罪事実該当者とみなした措置が必要
- 期限厳守:3ヶ月以内(政令で定める期間内)の確認完了
- 管理職による制度理解と責任者の決定
- いとま特例適用の判断基準を明文化
- 安全管理措置の具体的手順を策定
- 緊急時対応マニュアルの作成
職員・関係者への対応
- 全職員への制度説明と協力体制の構築
- 保護者への説明方針の決定
- 関係機関との連携体制の確認
- 専門家(行政書士等)への相談体制整備
いとま特例制度は、子どもの安全と教育・保育の継続を両立させる重要な仕組みです。
適切な運用体制を整えておけば、緊急時にも安心して対応することができます。
本格的な制度開始に備えて今のうちから準備を進めておきましょう。
なお、現職者といとま特例では、子どもへの接触ルールが異なります。
2つの違いを以下の記事で分かりやすく解説しています。
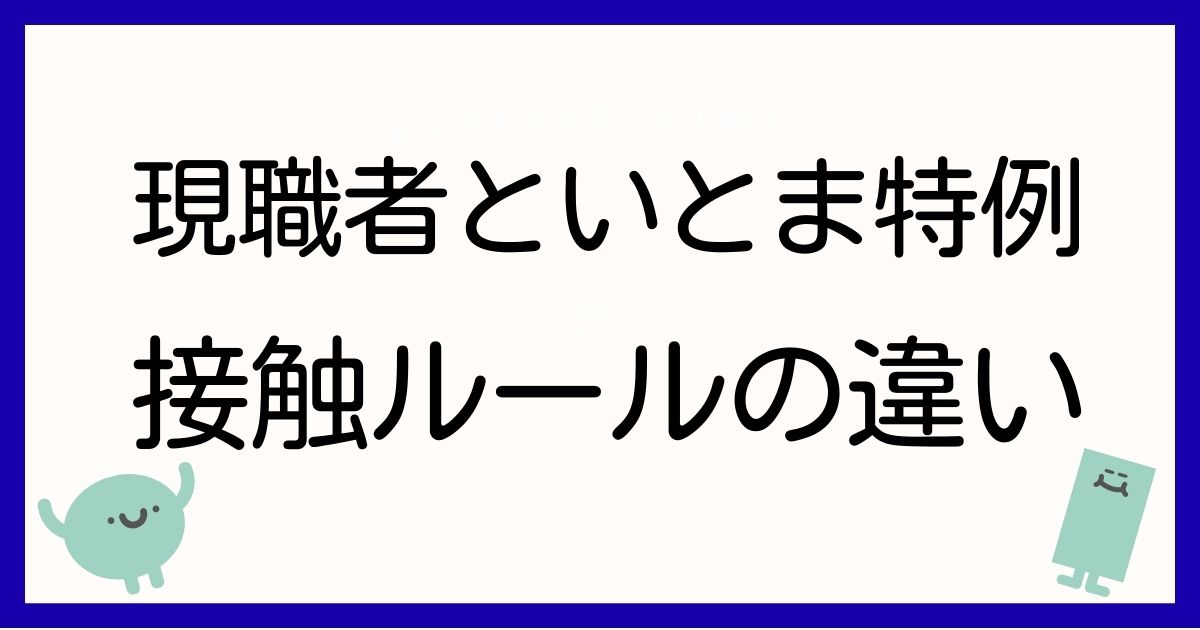
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請や運用はお任せください

この様なお悩みはありませんか?
- 日本版DBS(こども性暴力防止法)導入に向けて何から手を付ければいいのか分からない
- 人手不足で社員の性犯罪履歴確認や社員研修の企画・実施を任せられるスタッフがいない
- 民間事業者として日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けたい
- 情報管理規程や児童対象性暴力対処規程の作成方法が分からない
- 定期的に社員研修を実施して、社員の法令遵守意識を高めたい
このようなお悩みをお持ちの理事長、園長、施設長、事務長、社長は、ぜひ当センターにご相談ください。
当サポートセンターがお役に立てること
- GビズID取得支援:申請手続きのサポート
- 2つの規程の作成支援:ひな型をベースに、あなたの事業所に合った規程を作成
- 添付書類の準備代行:必要な書類の収集と整理をサポート
- 電子申請システムでの申請代行:システム操作から申請まで一貫してサポート
- 認定後の継続サポート:定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポート
 純さん
純さん貴社・貴園の実情をしっかりとヒアリングしたうえで、最適なサポートをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
教育施設: 幼保連携型認定こども園、認可保育園、認可外保育施設、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、音楽教室、英語教室、プログラミング教室、野球教室、サッカー教室、スイミングスクール、体操教室、武道教室、ボーイスカウト、チアリーディング、バレエ教室、ピアノ教室、ギター教室
福祉施設: 児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設
医療・保健: 小児科医院、心理カウンセリング施設
その他: こども食堂、児童図書館施設、学童保育、キャンプ施設、など。
LINEで簡単!全国どこからでも対応いたします
初回だけ、メールまたはLINEでお問い合わせください。
詳しいお話は電話でお伺いします。
北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, , 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, , 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄