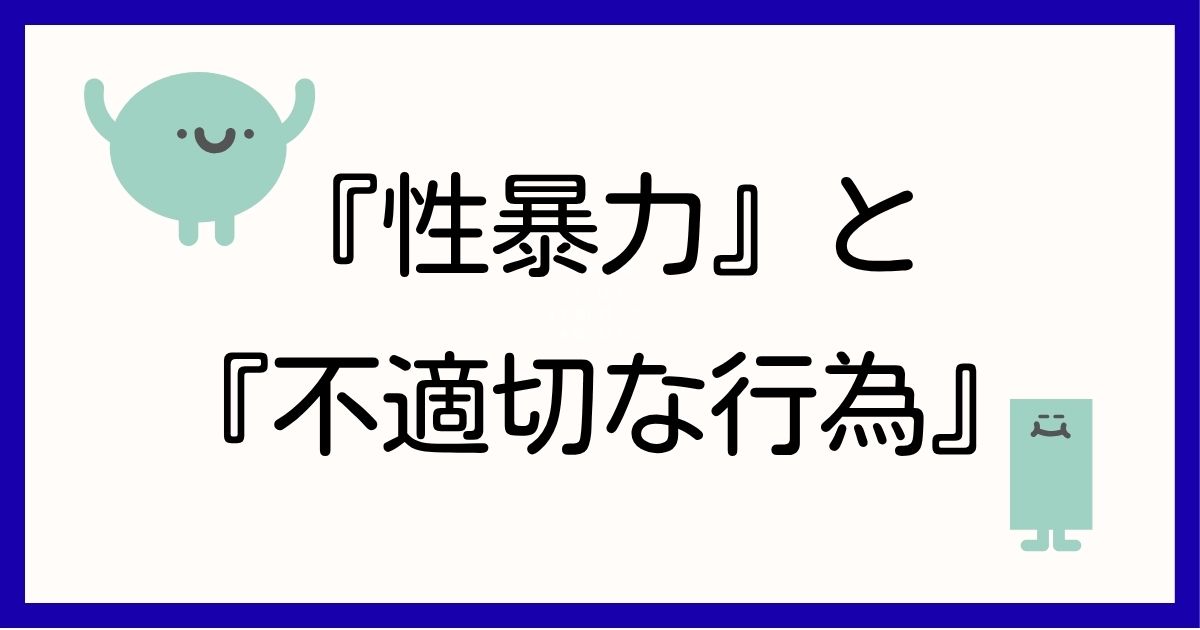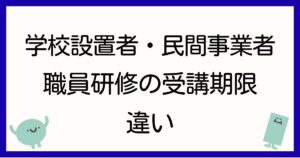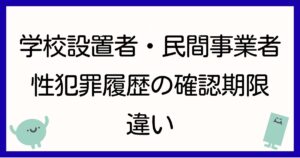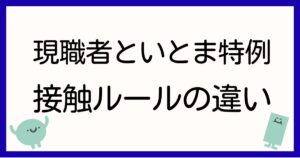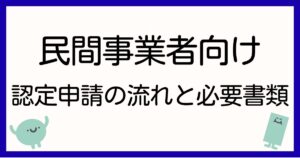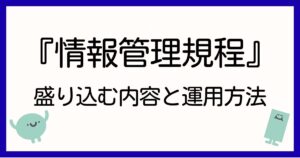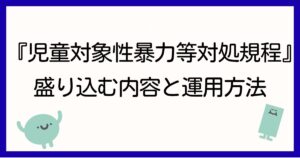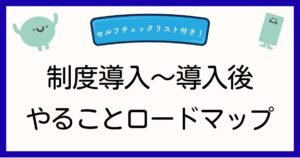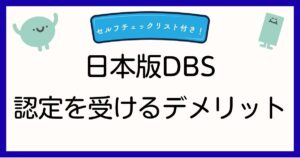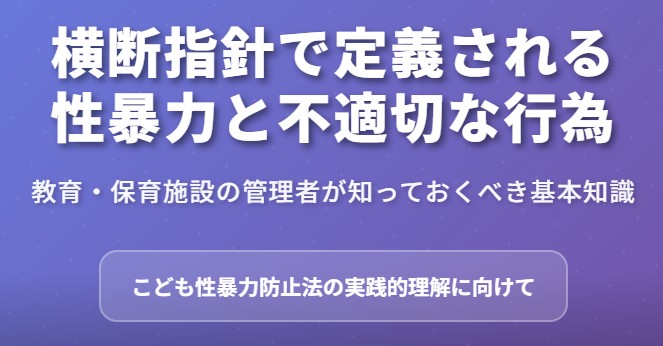
1. 横断指針とは何か
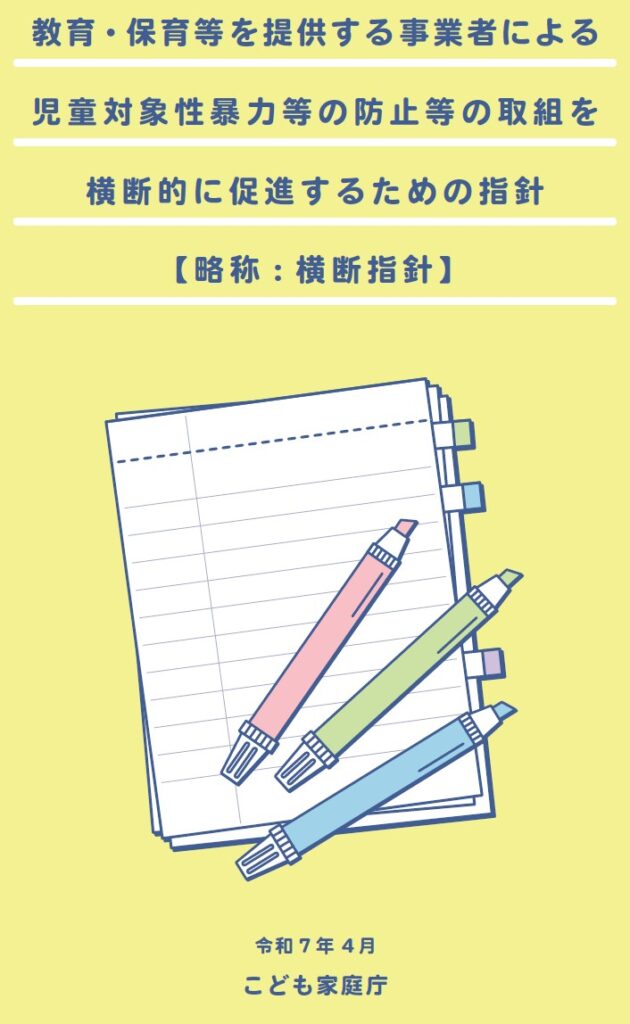
こども性暴力防止法の施行に向けて、教育・保育施設の運営者の皆さんにとって重要な資料が「横断指針」です。
この指針は、法律の具体的な運用方法を示した実践的なガイドラインとして位置づけられています。
横断指針の正式名称は「教育・保育等を提供する事業者における児童に対する性暴力防止対策に関する横断指針」で、こども家庭庁が作成しました。
これまで各分野でバラバラに対応されてきた性暴力防止対策を、教育・保育分野全体で統一的に取り組めるよう整備されたものです。
なぜ横断指針が作成されたのか
従来、性暴力防止については業界ごとに異なる対応が取られてきました。
しかし、こども性暴力防止法の施行により、学校、保育所、認定こども園、学童クラブ、塾、習い事教室など、すべての教育・保育事業者が統一的な対応を求められることになりました。
そこで、各事業者が具体的にどのような対策を講じるべきか、性暴力とは何か、どのような行為が問題となるのかを明確に示すため、横断指針が策定されました。
これにより、業界を超えて共通の理解と対応が可能になります。
対象となる施設・事業者
横断指針は幅広い教育・保育事業者を対象としています。
学校教育法に基づく学校はもちろん、認可保育所、認定こども園、学童クラブ、塾、習い事教室、スポーツクラブ、ベビーシッター事業など、児童と直接関わる教育・保育サービスを提供するすべての事業者が含まれます。
特に重要なのは、横断指針では「性暴力」と「不適切な行為」について明確な定義を示していること。
これまで曖昧だった境界線を具体的に示すことで、現場での判断基準を提供しています。
次の節では、この定義がなぜ重要なのか、そして具体的にどのような内容が定められているのかを詳しく見ていきます。
2. 横断指針における定義の重要性
これまで教育・保育現場では、「どこからが問題のある行為なのか」「どのような対応をすべきなのか」について明確な基準がありませんでした。
横断指針が「性暴力」と「不適切な行為」を具体的に定義したことで、現場に統一的な判断基準が提供され、適切な対応が可能になりました。
教育・保育現場での統一的な理解の必要性
従来、性暴力防止については業界ごとに異なる対応が取られてきました。
学校では教職員による児童生徒性暴力等防止法があり、
保育所では児童福祉の観点からの対応があり、
民間の教育事業者では各事業者の判断に委ねられていました。
しかし、こども性暴力防止法の施行により、学校、保育所、認定こども園、学童クラブ、塾、習い事教室など、すべての教育・保育事業者が統一的な対応を求められることになりました。
明確な定義が現場にもたらす効果
横断指針による明確な定義付けは、現場に以下のような効果をもたらします。
判断基準の統一化
これまで「グレーゾーン」とされてきた行為についても、性暴力なのか不適切な行為なのか、あるいは適切な教育・保育行為なのかを明確に判断できるようになりました。
予防的対応の実現
不適切な行為を「性暴力につながり得る行為」として位置づけることで、被害が発生する前の段階での対応が可能になりました。これは予防的な観点から非常に重要な意味を持ちます。
現場の迷いの解消
従事者が日常業務の中で「この接触は大丈夫だろうか」「この対応は適切だろうか」と迷うことが多かった状況から、明確な基準に基づいて判断できるようになりました。
組織としての対応方針の明確化
事業者が服務規律や研修内容を検討する際の具体的な指針が提供され、組織全体で一貫した対応が可能になりました。
被害の早期発見と対応
何が性暴力や不適切な行為に該当するかが明確になることで、被害の早期発見と迅速な対応につながります。
横断指針のこうした定義は、教育・保育分野全体での性暴力防止対策の質的向上に大きく貢献する重要な基準となっています。
次の節では、これらの定義の具体的な内容について詳しく見ていきます。
3. 横断指針が定める「性暴力」とは
横断指針では、性暴力について従来の概念を大きく拡張した定義を示しています。
これまで「性暴力」というと犯罪に該当する行為のみを想像しがちでしたが、横断指針ではより広範囲な行為を性暴力として位置づけています。

性暴力の基本的な定義
横断指針において、「性暴力」とは、犯罪に該当するものだけでなく、犯罪に該当せずとも、「(被害児童である)本人の意に反した性的な言動」が行われることを含むとしています。
この定義の重要な点は、犯罪として立件されるかどうかに関わらず、児童にとって「意に反する」性的な言動があれば性暴力と捉えるということです。
「意に反する」の幅広い解釈
横断指針では、「意に反する」について、被害児童が「嫌だ」と伝えた場合だけではなく、以下のような状況も含むとしています。
- 行為の意味を理解していない
- 嫌だけれども断れない
- 逃げられない
- 応じざるを得ない
- 性的手なずけによって誘導された場合
この解釈により、児童が明確に拒否の意思を示していない場合でも、児童の発達段階や置かれた状況を考慮して性暴力と判断される可能性があります。
接触型と非接触型の性暴力
横断指針では、「性暴力とは必ずしも、直接身体や性器に接触する行為であるとは限らない」と明記し、以下のような非接触型の性暴力も含むとしています。
非接触型の性暴力の例
- わいせつな言動
- 性器の露出
- ポルノや性行為を見せること
- のぞき、盗撮等
これにより、身体接触がない場合でも性暴力として対応する必要があることが明確になりました。
性別を問わない被害・加害
横断指針では、「性別を問わず性暴力の被害者となり得るものであり、加害者の性別は被害者の異性とは限らない」ことも明記しています。
これは、男性から女性への加害というステレオタイプにとらわれることなく、あらゆる性別の組み合わせで性暴力が発生し得ることを示しています。
16歳未満の児童に関する特別な考慮
横断指針では、16歳未満の児童について特別な注意を払うよう求めています。
「16歳未満の児童については、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力が十分に備わっているとは言えないため、仮に本人の同意がある場合であっても、性的行為が犯罪や性暴力となることに留意が必要である」
この規定により、たとえ児童が同意したように見える場合でも、16歳未満であれば有効な同意とは認められず、性暴力として扱われることになります。
横断指針における性暴力の例示について
横断指針では、7ページに「性暴力の例」として図表が掲載されており、「犯罪に該当し得る」行為と「犯罪に該当するとは限らないが性暴力に該当し得る」行為が具体的に示されています。
ただし、横断指針では「上記はあくまで例示であり、実際に個別の事案で犯罪が成立するか否かは、司法機関において判断されるものであり、上記分類は、事業者の対応方針の例を示すために分類している。事業者の対応方針は、個々の事情に応じて判断されるものであるため、例示にとらわれることなく、個別の事案ごとに対応を検討することとなる」との留意点が示されています。
このように、横断指針が定める性暴力の概念は、従来の狭い定義を大幅に拡張し、児童の権利保護を最優先とした包括的なものとなっています。
現場では、この広い定義を理解した上で、適切な判断と対応を行うことが求められます。
4. 横断指針が定める「不適切な行為」とは
横断指針における「不適切な行為」は、性暴力の予防的な観点から設けられた重要な概念です。
この概念により、実際に性暴力が発生する前の段階で適切な対応を行うことが可能になります。
不適切な行為の基本的な定義
横断指針では、「不適切な行為」を「性暴力につながり得る行為」として定義しています。
そして、「事業者において、性暴力につながり得るような不適切な行為についても対応することで、性暴力の未然防止につながる」としています。
この定義の重要な点は、不適切な行為そのものが直接的な被害を与えるものではなくても、将来的に性暴力へと発展する可能性があるため、予防的な観点から対応が必要だということです。
横断指針が示す不適切な行為の具体例
横断指針では、不適切な行為について3つの分類で具体例が示されています。
身体接触等に関する不適切な行為
業務上、接触が不必要な事業の場合
- 児童の身体に接触をしない
業務上、接触の必要がある事業の場合
- 児童に対して、業務上不必要な接触を行わない
- 不必要な接触の例として「胸、脇、腰、でん部、大腿部等を触る、抱きしめる、頬ずりする、膝に乗せる、おんぶする、マッサージする等」
移動に関する不適切な行為
- 不必要に、児童を1対1になる状況で車に乗せない
- 従事者による児童の送迎を行う場合には、予め又は事後的に、どの児童の送迎をいつ行ったか、管理職等へ報告させるルールを設ける
その他の不適切な行為
- キャンプ等宿泊を伴う行事等は、引率者を複数人とする
- たとえ児童から求められた場合であっても、事業所外で私的に児童と会う、SNSや連絡先を交換する、性的・肉体的な関係を持つといった行為をしない
業種による配慮と例外規定
横断指針では、不適切な行為について重要な留意点を示しています。
業種による配慮
「児童への身体接触に関する考え方は、業種によって様々であることから、現場が過度に委縮することがないよう留意しつつ、各業種のガイドライン等で具体的に検討・議論し、適切な身体接触の内容について、共通認識を形成することが有効と考えられる」
例外的な状況への配慮
「『不必要に、児童を1対1になる状況で車に乗せる』等、不適切な行為の例として挙げた行為のうちいくつかは、やむを得ない状況下においては許されることもある。
ただし、その場合でも組織的に情報共有しながら行うなど、性暴力につながらないよう歯止めをかけるルールを定めて、運用することが求められる」
愛着形成への配慮
横断指針では、特に保育現場での愛着形成について配慮した記述があります。
「児童から身体接触を伴う行為を求めてきたとき、愛着に課題がある児童などの場合には、それを無下に断ることが適切ではない場面も想定されるが、例えば膝に乗ってきた場合には、『お膝の上じゃなくて、隣に座ろうね』と言いながら、隣に座らせて、必要に応じて手をつなぐなどして安心感を提供することや、愛着形成に必要なスキンシップの範囲について保護者や職員が共通理解を形成するなど、性暴力の疑いが起こらないようなかたちで、児童とのスキンシップを工夫することも考えられる」
不適切な行為の重要性
横断指針では、不適切な行為について以下の重要な認識を示しています。
「不適切な行為は、『性暴力に該当しない行為』と捉えるのではなく、児童の人としての尊厳を踏みにじる行為になり得ることに留意することが重要である」
また、実際の対応においても「不適切な行為に対しても、未然防止の観点で真摯に対応する。当初は『不適切な行為』のみと思われていたものの、調査をしていく中で、性暴力が発覚する場合があることに留意する」としています。
このように、横断指針が定める不適切な行為は、性暴力防止のための重要な予防線として位置づけられており、現場での適切な判断と対応が求められています。
5. 16歳未満の児童に関する特別な配慮
横断指針では、16歳未満の児童について特に重要な配慮事項を明記しています。
この規定は、児童の発達段階を考慮した内容であり、現場での対応において極めて重要な意味を持ちます。
基本的な考え方
横断指針では、「16歳未満の児童については、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力が十分に備わっているとは言えないため、仮に本人の同意がある場合であっても、性的行為が犯罪や性暴力となることに留意が必要である」と明記しています。
この規定により、たとえ児童が「同意した」「嫌がっていなかった」ように見える場合でも、16歳未満であれば有効な同意とは認められず、性暴力として扱われることになります。
意思決定能力の2つの要素
横断指針では、性的行為に関して有効に自由意思決定をするための能力について、以下の2つの要素が必要としています。
- 行為の性的な意味を認識する能力
- 行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手方に対処したりする能力
年齢による違い
13歳未満の場合
上記①に行為の性的な意味を認識する能力が備わっておらず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力が一律に欠けている
13歳以上16歳未満の場合
上記①の行為の性的な意味を認識する能力が一律に欠けるわけではないものの、②の相手方との関係において適切な判断をする能力が十分でなく、相手方との関係が対等でなければ、有効に自由な意思決定ができる前提となる能力に欠ける
現場での実践的な意味
この規定により、教育・保育現場では以下の点が重要になります。
- 「児童が嫌がっていなかった」「児童から求めてきた」という理由で不適切な行為を正当化することはできない
- 16歳未満の児童に対しては、たとえ児童が親しみを示してきても、従事者は常に適切な距離感を維持する責任がある
- 組織として16歳未満の児童への対応について明確なルールを設け、すべての従事者が共通の認識を持つことが重要
この16歳未満の児童に関する規定は、横断指針の中でも特に重要な内容であり、現場での適切な理解と実践が児童の安全確保につながります。
6. 施設運営者として知っておくべきポイント
横断指針の定義を踏まえ、教育・保育施設の運営者の皆さんが実際に取り組むべき重要なポイントをまとめます。
横断指針は単なる理論ではなく、現場での実践を前提とした具体的な指針を示しています。
経営者・管理者の責任と認識
横断指針では、「児童に教育・保育等を提供する施設の設置者・事業の運営者は、従事者による児童への性暴力が、被害児童に生涯にわたって回復し難い心的外傷等を与え得る重大な人権問題であるとともに、適切に対応しないことが重大な経営リスクとなることも認識し、未然防止・早期発見、性暴力の疑い発生時の適切な事実の有無の調査、児童の保護及び被害児童への支援を行うことが重要である」としています。
これは、性暴力防止が単なる法的義務ではなく、経営上の重要課題であることを明確に示しています。
横断指針の定義を踏まえた組織運営
横断指針の性暴力と不適切な行為の定義を基に、自組織の服務規律や行動規範を見直し、具体的で実践的なルールを策定する必要があります。
研修・教育での活用
横断指針では、「全ての従事者(パートタイム、アルバイト、ボランティア等を含む)が、こどもの権利を理解し、児童への性暴力加害の抑止や、性暴力の疑いが生じた場合の対応に関する理解を深め、未然防止・早期発見につなげることが重要である」としています。
研修内容として以下が挙げられています。
- 人権及びこどもの権利
- 性暴力の定義や事例、不適切な行為の例、被害の深刻さ
- 性暴力防止に係る服務規律等、処分・措置に関する規定
- 加害につながり得る要因
- 性暴力行動の背景にある「思考の誤り」
- 日常観察におけるポイント
- 報告ルート等の周知
業種による特性への配慮
横断指針では、「児童への身体接触に関する考え方は、業種によって様々であることから、現場が過度に委縮することがないよう留意しつつ、各業種のガイドライン等で具体的に検討・議論し、適切な身体接触の内容について、共通認識を形成することが有効と考えられる」としています。
これにより、一律の基準ではなく、各施設の特性を考慮した対応が求められます。
実効性のある対策の実施
横断指針では、研修について「実効的な研修にするためには、いかに『自分ごと』と思えるか、性暴力の疑いが生じた際に取るべき行動をシミュレーションすることができるか等が重要と考えられる」としています。
また、「『自分ごと』にして、実際に行動できるようにしていくには、1回限りではなく、繰り返し行うことで意識等を定着させていくことが重要と考えられる」と継続的な取り組みの重要性を強調しています。
相談・報告体制の整備
横断指針では、「性暴力は、児童から被害を訴えることが非常に難いものであるが、児童等が性暴力被害や不適切な行為を訴えやすい仕組みとして、複数の相談ルートがあることが重要」としています。
具体的には以下のような工夫が求められます。
- 希望する性別の相談員に相談できる
- 手紙やメール、相談フォームなど、文字で相談できる
- 匿名で相談できる
- 相談したらどうなるかを児童が理解しやすい表現で周知する
事案発生時の適切な対応
横断指針では、「性暴力に対しては、被害児童を徹底して守り通すことを第一とし、加害行為を絶対に許さないという姿勢で挑むことが重要である。また、不適切な行為に対しても、未然防止の観点で真摯に対応する」としています。
さらに、「当初は『不適切な行為』のみと思われていたものの、調査をしていく中で、性暴力が発覚する場合があることに留意する」との重要な指摘があります。
継続的な改善の取り組み
横断指針の定義や考え方は、一度理解すれば終わりではありません。
法令の改正や社会情勢の変化、実際の事例を踏まえて、継続的に組織の取り組みを見直し、改善していくことが重要です。
また、横断指針では「本横断指針に記載されている取組について、各事業の事業形態を踏まえ、まずは効果的と考えられるものや実施可能なものから、取り組み始めることが重要と考えられる」としており、段階的な取り組みも推奨されています。
これらの横断指針の定義と考え方を正しく理解し、自組織の実情に合わせて適切に実践していくことが、真の意味での児童の安全確保につながります。
施設運営者のための横断指針実践ロードマップ
性暴力防止は重大な人権問題であり、経営リスクでもあることを認識
性暴力と不適切な行為の定義を踏まえた服務規律・行動規範の策定
パート・アルバイト・ボランティアを含む全従事者への継続的な教育
児童が相談しやすい環境と、従事者からの適切な報告ルートの整備
被害児童ファーストの姿勢で、不適切な行為から性暴力まで真摯に対応
定期的な点検と改善により、実効性のある性暴力防止体制を維持
横断指針の定義は一度理解すれば終わりではありません。
法令改正や社会情勢の変化、実際の事例を踏まえて、継続的に組織の取り組みを見直し、改善していくことが真の意味での児童の安全確保につながります。
まとめ
今回は、こども性暴力防止法の施行に向けて重要な「横断指針」の中から、「性暴力」と「不適切な行為」の違いについて解説しました。
最後に、押さえておくべき重要なポイントをまとめます。
横断指針の重要性
横断指針は、これまでバラバラだった各業界の性暴力防止対策を、教育・保育分野全体で統一して取り組めるよう作られた実践的なガイドラインです。
学校、保育所、認定こども園、学童クラブ、塾、習い事教室など、すべての教育・保育事業者が共通の基準で対応できるようになりました。
「性暴力」と「不適切な行為」の理解
性暴力の範囲拡大 従来の犯罪行為だけでなく、児童の「意に反する性的な言動」すべてが性暴力として扱われます。身体接触がない行為も含まれ、16歳未満の児童については本人の同意があっても性暴力となる場合があります。
不適切な行為による予防 「性暴力につながり得る行為」として不適切な行為を定義することで、実際に被害が発生する前の段階での対応が可能になりました。
横断指針は、児童の安全を守るための重要な指針です。
各施設の特性を考慮しながら、段階的に取り組みを進めていくことで、真の意味での児童の安全確保につながります。
ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、貴施設での性暴力防止対策を見直してみてください。
日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定申請や運用はお任せください

この様なお悩みはありませんか?
- 日本版DBS(こども性暴力防止法)導入に向けて何から手を付ければいいのか分からない
- 人手不足で社員の性犯罪履歴確認や社員研修の企画・実施を任せられるスタッフがいない
- 民間事業者として日本版DBS(こども性暴力防止法)の認定を受けたい
- 情報管理規程や児童対象性暴力対処規程の作成方法が分からない
- 定期的に社員研修を実施して、社員の法令遵守意識を高めたい
このようなお悩みをお持ちの理事長、園長、施設長、事務長、社長は、ぜひ当センターにご相談ください。
当サポートセンターがお役に立てること
- GビズID取得支援:申請手続きのサポート
- 2つの規程の作成支援:ひな型をベースに、あなたの事業所に合った規程を作成
- 添付書類の準備代行:必要な書類の収集と整理をサポート
- 電子申請システムでの申請代行:システム操作から申請まで一貫してサポート
- 認定後の継続サポート:定期報告や変更届など、認定後の手続きもサポート
 純さん
純さん貴社・貴園の実情をしっかりとヒアリングしたうえで、最適なサポートをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
教育施設: 幼保連携型認定こども園、認可保育園、認可外保育施設、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、音楽教室、英語教室、プログラミング教室、野球教室、サッカー教室、スイミングスクール、体操教室、武道教室、ボーイスカウト、チアリーディング、バレエ教室、ピアノ教室、ギター教室
福祉施設: 児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設
医療・保健: 小児科医院、心理カウンセリング施設
その他: こども食堂、児童図書館施設、学童保育、キャンプ施設、など。
LINEで簡単!全国どこからでも対応いたします
初回だけ、メールまたはLINEでお問い合わせください。
詳しいお話は電話でお伺いします。
北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, , 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, , 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄